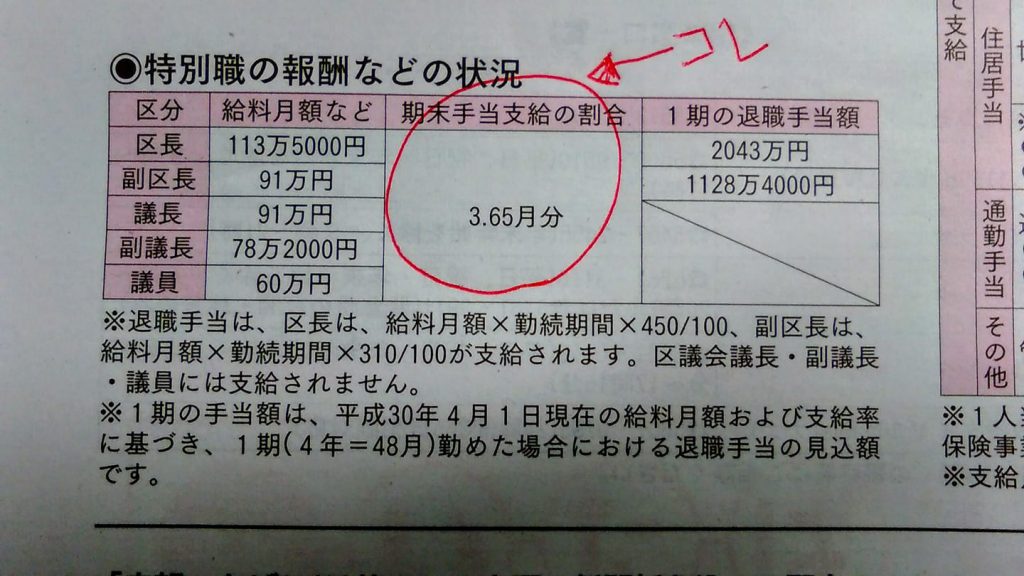今年(2018年)4月に板橋区議会に提出し、不採択とされてしまった、“あいキッズ職員にアイキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情” (ブログ 【不採択!】あいキッズ職員にあいキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情 http://shigakishinya.jpn.org/archives/2862 参照)
にかかる会議録を板橋区議会会議録サイトで見つけましたので以下に添付します。
そのままの添付のため議員名が敬称略となっていることをご了承ください。
区側が当初からあいキッズ職員に対するアンケートに後ろ向きで、そこから消極的な意見が積み重なり、結局、不採択となってしまったと読み取れました。
うーん、この結果、どうなのかなあ。。
完全に不採択にして陳情をばっさり切り捨てなくても、何らかの形であいキッズ職員さんたちの声を聞き取り、それを区民に公表するという作業は、あいキッズ事業の透明性確保や改善策を区民が一緒に考えるためには有効なのではないかと思うのですがいかがでしょう。
他の2件のあいキッズ関連の陳情と一緒に議論されているので、ちょっと長いのですが、あいキッズ事業に関心ある方は一読してみてほしいです。
——————
板橋区議会 平成30年 文教児童委員会 本文 2018-06-08
◯委員長
それでは、次に教育委員会関係の陳情審査を行います。
陳情第182号 あいキッズのおやつ(補食)提供時間を午後4時からでも可能とすることを求める陳情、陳情第183号 あいキッズの利用児童等にあいキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情、及び陳情第184号 あいキッズ職員にあいキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情3件を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明を願います。
◯地域教育力推進課長
それでは、陳情182、183、184号についてご説明をさせていただきます。
この3件の陳情でございますけれども、陳情者につきましては、記載のとおりの方でございます。
まず、182号につきましては、あいキッズを利用する児童について、現在、補食、おやつと呼ばれる方もいらっしゃいますけれども、これを5時に提供しているところでございます。この提供時間を5時だけでなく、4時からでも可能にするようにお願いをしたいというような趣旨の陳情でございます。
現状でございますけれども、あいキッズ、今申し上げましたように午後5時からおやつの提供ということになっております。このおやつ、補食につきましては、内容や量につきまして衛生管理、アレルギー等の対応、こういうようなことを考えまして、添加物の多い袋菓子を控えて、夕食に影響しない補食として摂取カロリーにつきましても150から200キロカロリーに抑えて消化のよい食品、あるいは季節感のある果物等を提供しているところでございます。
陳情の趣旨にありますように、4時に提供ということになりますと現在、あいキッズにつきましては、異年齢の子どもが学校から順次来た後に交流をするような時間をたくさんとるようにしております。こういう時間に影響が出てきますので、交流時間を確保するというような観点で5時からにしている。それから、5時前に提供しますと提供できる子どもと提供できない子どもが出てきて不公平感を抱くと、こういうような観点もございます。
さらには、提供したことによって、アレルギーを持っている子どもに例えば子ども同士で差し上げたりして食べたりすると事故のもとになるというようなこともございますので、現在のところ、5時以降に提供するというようなことでやらさせていただいているところでございます。
続いて、陳情の183号でございます。
こちらについては、あいキッズを利用している児童、あるいはその保護者から利用に関してのアンケートをとって、これをあいキッズで公表すると同時に、あいキッズの事業運営に反映をさせていただきたいというような趣旨でございます。
現況でございますけれども、あいキッズについては、私どもも魅力ある運営に改善していきたいというようなことがございまして、平成28年度から全52校、29年度も52校の児童、保護者を対象に、利用者満足度調査を10月から11月にかけて実施しております。
調査結果については、運営の改善につなげるというようなことが目的でございますので、私どもだけでなく、委託法人のほうにフィードバックはしておりますし、また区のホームページ、あるいはあいキッズのフェイスブックがございますけれども、こちらのほうに掲載をしたり、さらには私どもの窓口においても公開をさせていただいて、既にもう十分なご意見については伺っているというような状況だというふうに私どもは考えているところでございます。したがいまして、意見としてこのような形で出てきておりますけれども、私どもとしては、この利用者の満足度調査、こういうものの制度をさらに高める等して今までもやってきておりますので、これで十分いけるというふうに考えているところでございます。
続いて、最後の184号の陳情でございます。
こちらにつきましては、あいキッズ事業にかかわります職員の方に利用者アンケートというような形でアンケートをとって、その結果を区のホームページで公開して、あいキッズ事業の改善に反映をさせてほしいというようなことでございます。
私ども、この事業者のほうとは毎年、直接法人と区との間で一対一でいろいろヒアリングをさせていただいている、あるいは法人の代表者の方と一堂に会した形で会議をしていろいろご意見をいただいているところでございます。そういう中で魅力が高まるように、あるいはもう利便性がさらに向上するようにということで、児童や保護者の満足度、それから働いている方の満足度を上げるように意見は聴取しているところでございます。
私ども、この業務を委託しているところの職員に対してアンケートを行うということについては、請負契約ということで、私ども、直接指示ができない方々に対して優位な立場である区のサイドからアンケートを行うということは、ちょっと課題もあるというように認識をしているところでございますので、この件に関しましては、今あるやり方で十分意見も確認できておりますし、課題があるということで、これについては私ども、行うことは予定しておりません。
説明は以上でございます。
◯委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論を希望される委員は手を挙げて。
わかりました。ちょっと時間が早いんですけれども。
◯川口雅敏
私だけやってしまって。
◯委員長
足りるか、時間で。
◯川口雅敏
私は10分あれば十分です。
◯委員長
それでは、今、順次質問順序を示します。
まず、最初に川口委員。
◯川口雅敏
お昼までに終わらせます。
最初、これだけ補食について議会でも質問があったり、また陳情がこういうふうにあるわけですけれども、教育委員会としては、このあいキッズのおやつを廃止するということは考えたことがないでしょうかね。
◯地域教育力推進課長
現在のところ補食について、おやつについて廃止するということは考えているわけではございません。
◯川口雅敏
教育委員会は、あいキッズの保護者からの意見や要望をどのような方法で収集しているか、あるいはしていないのか。その辺はいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
ただいまの質問については、補食を含めてということですか。それとも補食のことに限ってということか。
◯川口雅敏
含めて。
◯地域教育力推進課長
平成28年度、29年度、利用者の満足調査ということで調査をさせていただいている中で、いろいろとデータのほうをいただいているところでございます。こういう中で、補食に関して申し上げますと、おおむね80%の方は今の補食でよい、あるいはどちらかといえばよいというようなデータもいただいているというような結果が出ているところでございます。
◯川口雅敏
では、次に、このあいキッズの利用者のアンケート、陳情では、利用者の子どもにアンケートをとってとありますけれども、教育委員会はあいキッズ利用者の子どもたちの意見や要望についてはどのように把握しているのか、その辺はいかがですか。
◯地域教育力推進課長
先ほど来申し上げているように、利用者の満足度調査で子どもの意見を吸い上げているところでございます。子どもについては、あいキッズについて利用頻度ですとか、それから楽しいですかとか、どういうようなものがもう少し加わるとよくなるでしょうかと、こういうような設問で意見は聞いているところでございます。
それから、私の説明の中で多少漏れていた点がございました。事業者によっては、さらに私どものアンケート以外にも独自でよりよいものにするということで、子ども、あるいは父母のほうから意見を募っているという例もございます。
◯川口雅敏
この職員のほう、あいキッズの現場の職員から情報はどのようにして把握していますか。いろんなことがあると思いますけれども、その辺はいかがですか。
◯地域教育力推進課長
事業者と直接一対一でのやりとりの中で、事業者でお勤めになられている方の満足度等をお伺いしたり、また改善する点があるかどうかをお伺いするというようなことは、基本的に毎年やらさせていただいております。
それと同時に、先ほども申し上げましたけれども、法人にお集まりいただいた会議の中でこういうようなあいキッズ、状況にありますよということで、さまざまなご意見もいただいていると。こういうもので反映できるものにつきましては、でき得る限り速やかに反映をさせていただくというような方針で臨まさせていただいているところでございます。
◯川口雅敏
あいキッズの現場の職員からは、おやつについて、補食についてどのような意見が上がっているのか、それを聞きたいのと、またそのほかの意見や要望に対して教育委員会はどのような対応をしているのか、その辺はいかがですか。
◯地域教育力推進課長
働いている方から補食についてのご意見を伺った場合、私のほうで申し上げましたけれども、現時点でさんさん、きらきらタイムの子どもが混在している中で提供するということは、事実上難しいと。やはりさんさんの子どもが帰られた後、きらきらの子どもに対して補食を差し上げることが一番間違いない提供の仕方だというようなお話を伺っているところでございます。
今申し上げたような件だけでなく、いろいろなところからさまざまな角度で要望が上がってまいりますので、それについては、先ほど来申し上げているとおり、私どものほうで対応できるものについては、基本的に対応させていただくというような方針で臨んでいるところでございます。
◯委員長
いいですか。
委員会の途中でありますが、議事運営の都合上、暫時休憩といたします。
なお、再開は午後1時といたします。
休憩時刻 午前11時57分
再開時刻 午後 1時02分
◯委員長
委員会を再開いたします。
質疑を続ける前に、理事者より、先ほどの竹内委員の質問についての補足説明を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
◯地域教育力推進課長
先ほどの説明、不足していて、大変申しわけございませんでした。
平成30年度のあいキッズの登録・利用状況の中で、竹内委員のほうから、きらきらタイムの利用者のうち、6時あるいは7時までの利用者は何人ですかということで、私が1,822人、1,571人というふうに、5月1日時点の人数ですけども、合計3,393人というふうに申し上げました。そうしましたところ、竹内委員のほうから、随分数字に乖離があるというお話がございまして、私のほうは、5月1日と4月28日の3日の違いですと申し上げたんですが、調べたところ、この大きな数字の違いは、例えば、長期休業期間中、朝8時からきらきらタイムの子どもをお預かりしますけれども、朝8時から5時までの間の子どもだけで1,050人いらっしゃいます。要するに、6時、7時まで学童としてとどまるようなことのない子どもの数が2,000人ほどおりますので、それだけの違いがあると。なお、5月1日と4月28日の違いは、おおむね60人ほど実はございます。正確な数字としては、今申し上げたとおりでございます。失礼いたしました。
◯委員長
しっかりやってくださいよ。
◯中野くにひこ
まとめて3点ほど質問をさせていただきます。
まず、第1点目ですけども、陳情の一番最初の部分で、説明の中で、午後5時からうちは補食をしているわけですけど、その理由の説明の中で、交流の時間に影響を及ぼすとあるので、ちょっと具体的に詳述していただければなと思います。その際に、補食はおやつとしてどのようなものが出るのか。例えば、大人であれば、物によっては夕食を食べる前に血糖値がすごく上がる食べ物もあるんです。お子さんはどうなのかということ、これが1点。
2番目なんですけれども、2番目の陳情の中で、十分に利用者の満足度調査をやっておりますというお話がございました。であるならば、具体的に親御さんのどのような要望について施策に結びつけたのか、具体的なエピソードがあれば教えていただきたいと、これが2点目です。
3点目は、職員にあいキッズの利用アンケートを聞くというのは、請負という形の流れの中で、介入できませんと説明がございました。これは、一番最初の協定書の文言の中に、このようなコンプライアンスが入っているのかどうかの確認でございます。
以上3点、よろしくお願いします。
◯地域教育力推進課長
それでは、中野委員の3点について答弁申し上げます。
まず、一つ目の交流の時間ですけれども、子どもが低学年の方からおおむね15時40分ぐらいからあいキッズのほうにやってまいります。高学年になればなるほど、あいキッズのほうにやってくる時間が遅くなります。
まず、あいキッズは、父母のほうからの要望等もあって、学習の習慣を身につけてほしいということで、来てから30分程度は宿題をしたり、あるいは自分で自習をしたりというようなことで、まず気持ちを落ち着かせたりしながら、上位の学年の子どもが来るのを待っております。上位の学年の方が来て、その自習の時間が済んだ段階から交流の時間ということで異年齢で始めますので、そこの部分で補食を提供すると、交流そのものができなくなるというようなことがあったりして支障になるというようなことでございます。
それから、補食の中身ですけれども、お煎餅ですとか、ドーナツですとか、チョコレートケーキですとか、あと果物等が出てくるというのが意見の中に出てまいります。そういうような簡単な食べ物だというふうにご理解いただければと思います。ある程度カロリーがあって、簡単に食べられるものと。
それから、2点目の意見を吸い上げている中で何か改善に結びついたものがあるかというようなお話ですけども、アンケートの中には直接はないんですけれども、一時期、長期休業期間中等に食事の提供ができたりできなかったりということで、あいキッズで違いがございました。要するに、お勤めをされている父母の方がお弁当をつくらなきゃいけないというのはなかなか大変なこともございますので、食事の提供ができないかというような要望を受けて、そういうようなことをいろいろ意見を伺いながら修正させていただいて、今夏休み等は、どこのあいキッズでも、きらきらタイムに登録されているお子様については、食事等の提供をし、希望をすればですね、配食のサービスが受けられるというように改善がなされております。
それから、3点目の請負契約ですけれども、協定書の中に何かそういう記述があるかというお話ですけれども、そういうものは実際にはございません、協定の中には。ただ、契約そのものが請負契約ですと、やはりそこで私どもが指示すると、いわゆる偽装請負というような形で法的に問われる可能性がございますので、私どもとすれば、そういうところの法人の責任者等とやりとりをして、必要なことはお話をさせていただくというような対応を自治体としてとらせていただいているということでございます。
◯中野くにひこ
よくわかりました。参考にしたいと思います。
最後ちょっと押しなべて、まちの方からこの間、次のようなお声を聞くんですね。当然、あいキッズ運営の流れの中で、安心・安全という形で、これしちゃいけない、あれしちゃいけないという形でお子さんに対してかなり厳しく、当然事故は起こせませんので、そのバランスがあるのかなという形で。現に子どもはつまらないので、前の公園のところで遊んでいるという切実なご父兄のお話も聞いたんですけども、そこら辺の部分についての認識というのはございますか。この2番目のいろんな父兄のご要望云々という話の流れの中で、そういったご意見はありませんでしたでしょうか。
◯地域教育力推進課長
あいキッズに通われていて、子ども、そのものがつまらないということで来れなくなったという例もないことはないというふうに私のほうでも聞いているところでございます。ただ、来ていただければ、その子どもも楽しんでいただけるような、そういうようなプログラムを組むような形で私のほうも法人等にいろいろお願いをしてまいりますので、もし具体的にそういうお話があるんであれば、私のほうに一言かけていただければ、対応のほうをしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◯高橋正憲
すみません、私、あんまりこれ、よくわからないので、そういうのを含めて聞きたいと思うんですが、これは、前身は学童クラブでしたよね。多分ね。そういう流れの中で、このあいキッズというのができて、学童クラブの場合は、ほとんど区が経営していたというか、区の職員でやっていたという部分ですよね。それが今度は委託をするようになったんですけど、委託する場合は、今、協定書、何かいろいろとやっていただく、運営するに当たっては、こういうことをやる、こういうことをやるという一つのものがあると思うんだよね。それにのっとって契約をして、運営してもらっていると思うんですよね。ですから、ごめんなさい、そういう文書をちょっと資料としていただきたいんです。
それと、やっぱり契約ですから、何年契約とかってありますよね。これは何年ぐらいの契約になっているのかということと、協定書がないというんだけど、学童クラブの場合は、要するに父母会とかいろんなのがあって、何かあれば話し合ったりなんかして前に進めていくという、そういうことがあったけれども、今回のように、ある程度委託する委託条件の中で運営してもらっているから、何かあったらこっちから言うという話はなかなか難しいと、そういうような話があって当然だと思うんです。
例えば、そういうふうないろんな問題を抱えながら、契約が満期になるよね。その契約時に、そういうようないろんな問題を加味して、条件として契約をしていくような、そういうようなことでやられているのか。
それと、もう一つは、満足度調査をしていますよという話で、おおむね80%はみんな満足しているんだと、こういうような話がありましたけれども、それでいいんですか。というのは、やはり我々が目指すのは、皆さんに利用してもらっているんだから、皆さんに満足してもらえる、そういうようなことで努力をしていくべきだろうと、そういうことで話を聞いていくべきだろうというふうに僕は思うんです。
ですから、例えば食事の件について出ています。4時からはできないのかという話も、いろんな条件を含めて、できる部分であればやっていったほうがいいし、どうしてもできないんだったら、何ができないのかということをいろいろと検討してみて、次の契約とか、いろんなときに生かせていけばいいのかなと。ただ、それは4時からやるといろんな問題があるので、やっぱり5時が一番いいんですと、そういうような結論であれば、それはそれでいいんですよ。ただ、今言ったように、4時からやってもらいたいという父兄がたくさんいるとするならば、その辺もやっぱり考えていったほうが僕はいいだろうと思う。
ただ、それについて、契約が新しく変わるときに、その辺もその業者と協定の枠組みの中に入れていかなきゃいけないというのであれば、やっぱりその契約更改のときにやっていかなきゃいけないでしょう。それを全て投げやりで任せちゃうんだという話ではないと思う。
だから、80%は満足しているけれども、あとの20%をいかに100%に近づけていくかという努力はやっぱり僕は一番大事であって、その辺について、どういうような形をとれば、今契約がこうなっていて、契約がある以上はできないんだよというような話があれば、じゃ、どういう形にしていけばできるのかということもやっぱり僕は考えていったほうがいいと思うんですよ。行政側としてね。その辺の3点ぐらいについてお伺いします。
◯地域教育力推進課長
ただいまのご質問ですけれども、あいキッズにつきましては、委員ご承知のとおり、昔、学童クラブというような形で直営でやられていたものでございます。平成21年から、それが少しずつ今の形に変化をしてきたと。児童館そのもののあり方を乳幼児に基本的に特化していくという中で、学童については今の形で委託でということでなされてきました。
先ほど、協定書の中にないというお話が冒頭出てきましたけど、あれは、中野委員のほうから、偽装請負、要するに請負契約をする中で、何か指示をしていい悪いというようなことが協定書の中にあるのかというようなご質問だったことに対して、ございませんというふうに申し上げたものでございます。そこは、誤解のないようにひとつお願いしたいと思います。
どういう形で業者を選定してきたかということなんですけれども、学童クラブから今のあいキッズに変わる段階で、基本的にやっていただきたい仕事について、私どものほうで形を決めまして、その上で業者のほうからプロポーザルを受けております。プロポーザルを受けて、その中で業者を決めてきたということです。そのプロポーザルの委員の中には、当該学校にかかわる父母の方にも入っていただいて決めてきたという経緯でございます。
そういう中で、何か私どもの決めたこと以外に提案があるかどうか、そういうものを含めて法人を決めたという経緯がございます。そういう経緯でございますので、その予定したとおり法人が提案どおりのことをやられれば、一定の満足度は得られるということに多分なるんだろうと思っております。
満足度の調査でございますけれども、今私の手元に29年度の調査がございますけれども、現在あいキッズの運営を受託している法人に満足していますか、「はい」という方が55.9%、「どちらかといえばはい」という方が31.2%ですので、87%の方が基本的には満足していただいているという答えが出ております。
ただ、一方で、委員がまさにおっしゃったとおり、残りの13%の方は満足していないんだと。その満足度を上げるために何をしているんだという、そういうようなお話が出てまいりました。基本的には、この法人との契約は1年契約をしているんですけれども、その契約がきちんとなされているんであれば、5年間やりましょうというような中身になっております。ですから、基本的には、子どものことを考えて、余り法人が変わらないようにというような視点も加えてのプロポーザル、選定というふうにお考えいただければと思います。
その上で、余りにもその法人の対応が悪いという場合には、5年を待たずして3年で打ち切って、新たに選定したケースもございます。それから、5年を超えて、やっぱりやってほしいというようなご意見があれば、これは5年を超えてというような契約もしているところでございます。
ですから、法人のその内容によって、実施した事業によって大分変わってくるんですけれども、そういうような状況でございまして、その選定のときに、新たに13%の方がこういう点をプラスしてできないかというようなことで提案をしていただいて、そういうお答えをいただければ、またそういうような事業者が選ばれてくるんだというふうに私のほうは考えているところでございます。なかなか難しい質問でしたので、うまく答えができませんけども、私どもの選定の方法と、それから改善の仕方というのは、今申し上げたとおりの内容でございます。
◯高橋正憲
わかりました。1年契約で、問題がなければ5年ぐらいまでで、子どもたちが喜ぶのであれば5年以上ありますよというような、そんな話だろうと思うんです。その中には、1年契約ですから、最低でも1年に一遍ぐらいの満足度調査というものをやられているのかなと、そういうふうに思います。そうなると、その満足度調査の中で、いろいろ問題が出てきたことに対して、善処することはできるよね、当然ね。ですから、1年ごとの契約なんだから、契約書はやっぱり1年ごとに結ぶわけでしょう。そうですよね。であるならば、その中に、当然やってもらいたいこととか、やるべきこととか、そういうものが出てくれば、その協定書というか、契約するときに、その部分を加えて契約してくるということは今までやられてきているんでしょう。どうですか。
◯地域教育力推進課長
おっしゃるとおりでございます。私どものとったアンケートについては、各事業者のほうにフィードバックをさせていただいております。したがいまして、そこで出てきた要望等については、事業者も、当然承知しているところでございますので、例えばあいキッズにもっとこういうものが欲しい、例えば遊具が欲しいとか、本が欲しいと、そういうような答えが出てくれば、そういうものを事業者のほうで用意して、子どもが満足できるような、そういう体制をとらせていただいているところでございます。
◯高沢一基
よろしくお願いします。
まず、補食についてなんですけれども、先ほどもお話がありましたように、果物とか、お煎餅とか、ドーナツとかというものを出しておられるというお話で、消化のよい物と最初おっしゃっていましたけど、消化にいいかどうかちょっとあれかなという気もしないでもないんですが、そういったお話が出ておりました。
まずは、現状も含めてちょっとお聞きしたいんですけど、他区の状況。特別区23区ということで、ちらっと聞いたところによると、5時以前に出すところが大多数だというふうに私は聞いているんですけれども、その辺で具体的に何時からが何区であるか、板橋区のように5時からは何区あるとか、そういった形で教えていただきたいと思うのと、板橋区においては5時に補食を提供しているということの理由に、先ほど来ありましたように、交流時間の確保、公平感、アレルギー事故の防止等の課題があるから5時だというふうにご説明されているんですが、他区で5時以前に出しているところがこれらの課題を克服できているのか、どのように分析をされているか、ご見解をお聞きかせください。
◯地域教育力推進課長
他区の状況でございますけれども、17時、私どもと同様な出し方をしている区が4区ございます。それから、一切出していない区が3区ございます。そうすると、合計7区ですので、残りの区がもう少し早い段階で補食を出しているということになるわけでございます。
ただ、私どもとの運営の違いが、いわゆる学童として運営しているところがございますので、全児童が一堂に会して私どものほうは5時までの間は交流プログラム等を実施したり、学習をしたりしていただいておりますけれども、学童だけやれば、お勤めになられている父母の方だけですので、ちょっとその辺は比較にならない部分もございますので、数字としては今申し上げたとおりでございますけれども、内容についてはちょっと違いがあるということだけご認識いただければと思います。
◯高沢一基
17時以前で16区ということですけど、その17時以前の時間もちょっと、区数を教えていただきたいのと、あと全児童対策をやっていない学童だけだというお話もありましたけど、全児童対策をしていて5時以前に補食を提供している区はないということで理解してよろしいでしょうか、お聞きかせください。
それとともに、もしそうであれば、先ほど来言っていますように、交流時間の確保等の不公平感、事故防止とおっしゃっていましたけれども、それは全児童対策としてやっている区がもし5時以前であれば、どういう状況になっているかお聞きかせいただきたいと思います。
◯地域教育力推進課長
大変申しわけございません。全児童対策をしているかどうかというのは、ちょっとまだつかんでおりませんので、後日調査をさせてから、お答えのほうをしたいと思います。
それから、補食の提供時間でございますけれども、16時にかかるような区が6区です。それから、15時ぐらいから残りの10区、そうすると10区になりますかね、これが15時台というようなことでご理解いただければと思います。
◯高沢一基
ありがとうございます。全児童対策とともにやっていて5時以前があるかどうかというのは、後ほど調べてお答えくださるということなので、よろしくお願いいたします。
把握されていないんだったら、先ほどの答弁はおかしいですよね。学童保育をやっているから5時以前に提供できているというお話をされたので、だけだからということを把握されているんだなという前提でお聞きしているので、そこら辺は正確にご答弁お願いしたいと思いますし、あるのかないのかも私も調べていないので、全体条件の情報というのは大切だと思うので、お調べいただいて、後ほどでも結構ですから教えていただければと思います。
そうなってくると、補食を出していないところもありますから、この全児童対策の有無によって考え方が変わってくるんですけれども、全児童対策でやっているところは補食なしというふうに判断をしているところ、あるいは5時以降というふうにやっているのか、あるいはそれ以前にあるのかということで、やはり議論が整理されてくるというふうに思いますので、そこは正確なところを後ほどまた資料でいただければと思います。その上で判断もしたいと思うところであります。
あと、今度、教育のほうでちょっとお聞きしたいんですけれども、生活習慣等でいろいろ指導されておられて、早寝早起きをしましょうというようなことを一生懸命声をかけられていますよね。具体的な時間はないと思うんですけど、何時ぐらいに就寝だとかというのはないとは思いますけど、早寝早起き、あるいは3食、規則正しい生活で食事をちゃんととりましょうとか、そういった指導をされていると思うんですけど、何かこういう生活指導の10のルールでしたっけ、何とかってあったかと思うんですけど、それに関して、夕食とか就寝時間について何か規定しているような、具体的な時間じゃなくて結構なんですけど、どういった教育を学校現場でされているかお聞かせいただきたいと思います。
◯地域教育力推進課長
子どもの生活習慣も私どものほうでいろいろ関与させていただいておりますけれども、具体的な時間についてはなかなか出てまいりません。今回の補食に関しても、時間がこの時間でいいという方も数多くいらっしゃるのも一方の事実です。それから、食事が早いので、この時間だと夕食を食べなくなるというようなご意見があるのも事実でございまして、皆さんのお勤めの仕方、それからお食事のつくり方、こういうものによって大分時間がずれてまいりますので、これを一概に何時がいい悪いというふうには私のほうは申し上げられませんし、ただ一方で、事業の中では、特定の時間でやらざるを得ないというような実態で、今は17時から補食のほうを提供させていただいているということでございます。
◯高沢一基
ありがとうございます。やむを得ない事情等や家庭それぞれで違うというのは十分承知しているんですが、基本的に、早寝早起きがいいですよと奨励しているわけですよね。違いますか。そこを確認したいのと、早寝ということであれば、やっぱり食べてすぐ寝るというのは健康上よくないかなと。食事はある程度早い時間に食べましょうというのが当然の指導といいましょうか、話になるかなと。100%やれという意味じゃなくて、そういう呼びかけをしているということですよねということはちょっと確認をしたいんですが、いかがでしょうか。
◯学務課長
私どもで、小学校入学前に、新入学に関するご案内ということで案内の冊子をつくってございます。新1年生ということですけれども、小学生の一日ということで、例えば書いてあるのが、起床は7時までに起きる習慣を、朝ごはんはエネルギー源であり生活リズムを整えますですとか、就寝につきましては9時までに寝る習慣をつけましょうというようなご案内をしているというところでございます。
◯高沢一基
それで全家庭を拘束できると私ももちろん思っていないんですけど、やっぱり児童の健全な生育のためには、ある程度そういう目安というのもお示しして、ご家庭のご協力、ご理解をいただくということも大事なのかなという気持ちを持っている一人なんです。そうなると、私も大体常識的に9時ぐらいかなというふうに思うんですけど、そうなってくると、やっぱり夕食の時間、おのずと7時ぐらいまでに食べ終わらないといけないのかなとか。これは常識的な範囲になりますから、それが正しいか正しくないかというのは言えないんですけど、そうなってくると補食がどうなのかなという議論にもなってくるかと思いますので、その辺はやっぱり学校現場で呼びかけていることとそごがあるといけないかなと思うので、ぜひそこはお考えいただければというふうに思います。
あとは、これはここで結論が出るもんじゃありませんけれども、そういう考えでいって、全児童対策で、ほかの区もなくて、どうしても先ほどの3条件が克服できないというのであれば、補食をなくすという判断、このやっていない3区がどういうご判断でされているか調べていないからわかりませんけれども、そういった問題も出てくるのかなと推測されますので、それはぜひ、場当たり的ではなくて、論理的に検討していただければありがたいと思います。
あとは、先ほどの交流時間の確保や不公平感とかアレルギー事故防止というのも、やろうと思えば、手だてを立てれば5時以前に補食を出しても、できないことではないというふうに私も思いますので、その辺の研究についてもぜひ深めていただきたいと思いますが、今の2点についていかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
今委員のほうからお話があった後段のほうからまずお答えさせていただきますけれども、17時にこだわっているというわけでもなく、子どもがそういう条件が整ったときには、例えば冬場などは4時30分で帰る子どもが多くなりますので、そういうときには早く繰り上げて差し上げたりしているのが実態でございます。
ですから、やはりいろいろとその実態に合わせて提供のほうはさせていただくように、十分よその区の状況も確認しながら調べた上で、最終的に出さないというのもありだというお話もございましたけども、今のところは提供することを前提に考えておりますけれども、検討させていただいて、答えのほうはきちっと出していきたいというふうに考えております。
◯高沢一基
ぜひその辺は研究していただいて、なおかつ本当に5時以前に出せないのかという、先ほどの課題をおっしゃっているわけですから、その課題の克服ができないのかどうかという検討もぜひ深めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
あと、もう一点だけ、ちょっと時間もあれですけど、1点確認なんですけど、職員からの意見聴取等についてなんですけど、最初は請負契約による課題があるというお話で、その次の質疑においては、偽装請負の可能性が指摘されちゃうおそれがあるみたいなご答弁をいただいたんですけれども、もちろん職員を指揮したり、命令したりとかすると、そう言われるおそれはあるのかなというふうに素人ながら思うんですけれども、職員から意見をアンケートなりで聞くということ、それ自体も偽装請負というふうに言われてしまうおそれがあるというのは、これはどういった考えでお話しされているのかお聞かせいただきたいと思います。
◯地域教育力推進課長
アンケートで聞くということが偽装請負だというふうに申し上げたつもりでなく、指示することが偽装請負になる、そういう、ある意味、強い立場の板橋区のサイドで直接働いている方々にアンケートをとるということはいかがなものかと。要するに、アンケートに対する答えも一定のものを求めているように相手が捉えたり、それから答えなければいけないという義務感を捉えられたりしてもうまくないんじゃないかというようなことで課題があるので、私どもはそういうことはやりません。そのかわり、法人のほうとはしっかりといつでも意見交換をしておりますし、法人の会議の中でもいろいろご意見をいただいている。その中で十分反映できるものは反映させていただいているということで、この184号については、ここに書いてあるようなことはやりませんというふうに申し上げたわけでございます。
◯高沢一基
確認なんですけど、別に偽装請負というふうに指摘されるおそれがあるからアンケートはしないということじゃなくて、法人とヒアリングしているので、それで十分ですと。直接聞かなくても、経営者から聞けば話がわかるんだという意味なんですかね。それであれば、それも一つの理屈ではあるんですけど、逆に言えば、職員さんの声を聞くというのも、別に請負でなければ、やっぱり経営者の方とは違う意見というのもあるのかなという気もするんですけど、そのあたりについてはどのようにお考えですか。
◯地域教育力推進課長
同じ答弁になりますけども、強い立場、ある意味上位にいる立場の区のほうから、働いている方々に直接意見を求めるというのはやはり課題がある、難しいんではないかなということで、私どもは実施しないというようなことでお答えをさせていただいているところでございます。
◯高沢一基
繰り返しになりますからこれ以上聞きませんけど、ぜひ現場の声の把握というのも、事業者さんを通してとおっしゃっていますけど、事業者さんを通すときにおいても、やっぱり現場の声と経営されている方の声って違う場合もありますのでね。そこはやっぱり吸い上げるようなところを、直接はだめだというならば、その辺の配慮も事業者さんのほうに伝えるべき必要もあるのかなという気もいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
◯松崎いたる
皆さん聞いているので、偏らないようにしたいと思うんですけど、おやつを出すということが、あいキッズの職員さんにとってどれだけの負担になるのかしらというのを聞きたいんですけど、どういう聞き方をすればいいんですかね。例えば、手間が大変ですよとか、時間的にかかるんですよとかいうことがあれば教えていただきたい。というのは、今回の陳情は、5時に出しているものもやりつつ、4時にも出してくださいということになると、単純に考えれば、職員負担が2倍になるんではないかと私は思ったんですけど、そんなことないですよ、あっさりと簡単ですよというんだったら、そういうふうに教えてほしいんですけど。
◯地域教育力推進課長
おやつを出す際なんですけれども、子どもたちを一定の場所に集めて、手を洗っていただいて、その上で、いただきますというような、ばらばらに食べるような、そういう食習慣ではうまくありませんので、いただきますということで一斉に食べて、最後に片づけるというようなことをしますので、今松崎委員がおっしゃったように、4時と5時ということになれば、当然そこの部分の時間、場所、これは2倍になるというのはご指摘のとおりでございます。
◯松崎いたる
学校で出すといったら、給食なんかがあるんだけど、給食の場合は、衛生管理とか結構きちっとやって、やりつつもそれでも何か危なっかしいなというところはあると思うんですけど、あいキッズの補食の時間なんていうと、たまに私も、学校に行ったときに、その時間帯を見たりなんかするんだけど、結構子どもらがちょこちょこ歩いている中を職員さんがおやつのお皿を持ちながら移動したりとか何か、ぶつかったらどうするのかしらみたいなふうに、はたから見ていると危なっかしくても、職員さんたちはなれているからそんなの苦もせずやっているんでしょうけど、大変だなと思いました。
もう一つ聞きたいのがあって、私も思い出すのは、何年か前にアレルギーの事故があったんですよね。それが私にとっては思いがけない原因だったんですよね。そのときもアレルギー対策というのはとっていたんですけど、原因がたしか果汁100%のピーチゼリーだと。果汁100%なのに、中に牛乳が入っていた。それで、牛乳アレルギーの子が発症しちゃって事故になったと。普通、果汁100%と書いてあれば、それ以外に入っていないと思うのが普通の感覚だと思うんだけど、実はよくよく見ると乳製品がちょこっと入っていると。そこまで気をつけなきゃ、アレルギー事故というのは防げない。各ご家庭だと、自分のお子さんのことですから気をつけているんでしょうけど、何人か集めると、そういう事故も起こっちゃうんだなと思った記憶があるんですけど、ただ、それ以来余り事故の話は聞いていないんですけど、その間にこのあいキッズが始まりましたでしょう。あいキッズでは、アレルギーの事故防止については、例えば研修を義務づけているとか、何かそういう対策があればちょっと教えていただきたいんですけど。
◯地域教育力推進課長
ただいま松崎委員からアレルギー対応についてのお話がございましたけれども、アレルギーについては最大限配慮すべき事項でございまして、中にはエピペン等もお預かりするような子どももいらっしゃいます。
補食に関してまず申し上げますと、食品の成分添加物について、提供にかかわる職員全員で確認するとともに、食物アレルギーを持つ児童のアレルギー物質との照合を確認して行うと。それから、プレートの色を変えるとか、そういうようなことで、見た目でアレルギー対応をしなきゃいけない子どもかどうかわかるようにするとか、そのような対応をさせていただいて、なおかつそれができない場合には、全て夏等は食事提供をさせていただくというお話をしましたけれども、ご家庭のほうからお持ちいただいて、それで食していただくというような対応をさせていただいているのが実態でございます。
◯松崎いたる
これは集団になっちゃうと、普通のご飯の感覚じゃ思わぬ事故があるので、これからもちょっと忘れないで対応はとっていただきたいなと思うんですけど、おやつについては十分リストもあるということなんですよね。だからやめちゃえとは私も思いませんけど、食事を提供するということは、それだけリスクが伴うものだという認識を持たないと、思わぬ事故が起こるものだなというふうに思います。
それと、次、陳情第184号の職員アンケートについてお聞きしたいんですけど、先ほどのやりとり聞いていて、なるほどなと思ったんですけど、私はこの陳情者が求めている職員アンケートのことで、職員の声を聞くというのはもちろんいいことなんですけど、ただ、課題があるとしたら、ホームページに掲載しなさいということになっているんですよね。子どもとか、親御さんの声だったら、こんな声がありましたとホームページに掲載してもさほど問題はないかなと思うんですけど、働いている職員さんの声を、たとえ氏名とか職場の学校の名前を隠したとしても、こういう声がありましたといったら、経営者から見れば、すぐ誰だか特定できるようなことになっちゃうんじゃないかと思うんですよね。もうこの陳情についてはやらないみたいなお話はされているんだけど、もし職員アンケートをホームページで公開するということになったとしたら、今私が言ったような職員の特定になって、職場で不利益な扱いを受けるということは考えなきゃいけないと思うんですけど、そのあたりは何か考えたことがありますか。
◯地域教育力推進課長
私どもは最初からやることは望ましいことじゃないということですので、考えたことはございませんでしたけれども、今松崎委員がおっしゃったように、設問によっては、この設問についての答え、こういう答えをしたというのがどなたか特定されるということになりますので、それはやはりうまくないだろうなというのは、私のほうも今のお話で十分理解したところでございます。
◯松崎いたる
すみませんね、間違いかもしれないんですけど、そう思っていたもんですから。
あと、これで最後にしますけど、ただ、そうはいっても、やっぱり職員からの声というのを区が全然聞かないというのもまずいわけで、もちろん聞いていらっしゃるという話だったんですけど、私は、その事業者との話し合いの中で聞くという話なんですけど、それだけじゃやっぱり1つ足りないところがあるなと思うのは、実際に現場で働いている職員さんが事業者に対して不満とか、あるいは問題点をつかんでいたときに、それはまずは雇用主である事業者に言うというのが筋かもしれないけど、それじゃ解決しないということもあると思うんですよ。要するに、内部通報ですね。公益通報。このパイプというのはしっかり保っておく必要があるんじゃないかと思うんです。先ほどアンケートのところで言った、誰それと特定されないような形で事業者の問題点を現場の職員さんに聞くということは、考えておく必要があると思うんですけど、その辺はどのようにお考えでしょうか。
◯地域教育力推進課長
私ども、ちょっと観点が違ってしまいますけれども、現場のほうには毎月、職員がいろいろな目でチェックをするという必要がございますので、伺っております。そういう中で、職場の雰囲気ですとか、そういう部分に何か通常じゃあり得ないような状態があったときには、何がしかそういうものを捉えて、法人のほうに、何かあるんじゃないですかとか、こういうやりとりもさせていただいております。そういう中でも、職員の方々の不満ですとか、そういうものを受け入れるつもりでございますので、それと、先ほど来申し上げているようなヒアリング、これである程度話のほうは通るというふうに理解しておりますので、今申し上げたようなやり方を通じて、あいキッズで働く方々の条件等については整備していきたいというふうに考えているところでございます。
◯安井一郎
質問させていただきます。このあいキッズ事業というのは、平成21年、最初に4校できて、この30年で1校減って51校、板橋区内全部の学校にあいキッズが配置されてできているわけですけど、過去には児童館、同じように学校内に児童館があれば、それで一番よかったんでしょうけど、私の知る限りでは、暗い夜道を子どもがあいキッズに行くために通っていて、交通事故にあったりという話が過去にありました。
子ども・子育て支援新制度に基づいた保護者の子育てと仕事の両立支援を区としてはあいキッズという形で始められて、もう10年たっているわけですけど、私は、1つ、区民にそれだけ親しまれているというか、愛着があるから、こういったような陳情も出てくるんだろうと思います。本来であれば、私らの世代だったら、茶だんすの中におやつが入っているからと、親に言われてそれをという時代だったんですけど、今は行政が子どもの面倒を見るという形でこういうふうに形をつくってやっていらっしゃるから、それに、このあいキッズという名前も、板橋のIをとって子どもたちということで、あいキッズ、皆さんもう誰しもご存じだろうと思いますけども、そもそも基本に立ち返って、なかったときのことを考えてみるのも1つ、問題を提起されているこの補食についても、それからアンケートについても、やっぱり時代が進んでいくから、そういう陳情も出てくるんじゃないかなと思います。
私が質問したいのは、あいキッズ事業って、補食のことで時間を決めてやっていらっしゃるというふうに、課長が先ほど来からずっと当然されていて、私は5時の時間というのと、それからアレルギー対策をきちっとされているということで、なおかつあいキッズの利用者の子どもたちのアンケート、それから職員のアンケートですけど、私が一番思うのは、現場を見ていて、子どもたちが一番正直だから。嫌いなものは嫌いって、あいキッズの職員を名指しで言いますよ。遊んでくれないもん、子どもが。だから、それぐらい子どもって正直だから、大人が心配するほどのことじゃないんじゃないかなと思うので、その辺の見解、課長はどう考えていらっしゃるか、それだけお聞きしたいんですけど。
◯地域教育力推進課長
今安井委員のほうからお話がございましたように、あいキッズもスタートしてかなりの年月がたちます。子どもも6年通う方もいらっしゃいます。そういう中で、顔と顔とがつながって、人と人とのつながりというものも感じられるようになれば、あいキッズが楽しくてしようがないというふうに感じる子どもも多くいらっしゃると思いますし、実際、アンケートの中でも、やはりあいキッズが楽しいという子どもも大勢いらっしゃいます。
ただ、一方で、先ほど来、評価していない方もいらっしゃる。子どもの中にも、やはり通いたくないという方もいらっしゃいます。ただ、それが本当に通うべきところがあって、要するに習い事があって、あるいは図書館に行きたいからとか、いろいろあると思いますけれども、そういうものがあっていらっしゃらないのであれば、私どもとしては、これはこれでいいと思うんですが、そうでなく、行き場がなくいらっしゃらないというのは、これは望ましいこととは私ども教育委員会のサイドとしては思っておりませんので、できる限り子どもに魅力あるあいキッズに、やはり常に常に新しいものを展開して、フレッシュな形で子どもに来ていただくというように努力は今後とも続けさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
◯竹内 愛
まず、補食についてなんですけども、先ほど課長の答弁で、早く繰り上げることは可能だと、それから実際にやっているというお話がありましたけども、その際には、きらきらとさんさんで差が出るという先ほどの公平感、それから不公平感、それとアレルギーの誤食のおそれ、こういった問題というのはクリアできた上で早く繰り上げることをやられているということでよろしいですか。
◯地域教育力推進課長
私の説明が舌足らずで申しわけございませんでした。冬場は4時30分までということで、早く帰る子どもがいれば、きらきらタイムの子どもばかりになると。そういう場合には、5時にこだわらずに、子どもを一堂に集めて、手を洗って、5時前でも補食のほうを提供していると、そういう例もありますよということをご紹介したわけでございます。したがいまして、今おっしゃいましたように、さんさん、きらきらの子どもが混在している中で提供しているというわけではございません。
◯竹内 愛
そうすると、混在している状況では早く繰り上げることはやっていないということでしょうか。私の認識だと、年度当初始まったころには、低学年のお子さんについては早い時間に補食を提供しているということを、やっているところは数週間というところもあれば、1学期というところもあると、そこはまちまちですと聞いているんですけど、それはやっていないということでよかったんですか。
◯地域教育力推進課長
今竹内委員がおっしゃったのは、恐らく昨年度ぐらいまでの話だと思います。といいますのは、小学校に入学したての子どもに対しての給食の提供の仕方が一部の学校で違っておりまして、量が少なかったりとか、なれていただくための提供をしているような学校がございまして、そういうところについては一部早く実施したというふうに聞いているんですけれども、ことしはそういう学校がほとんどなかったということで、私の知っている限りでは、17時以降、基本的にきらきらタイムの子どもだけになった段階で提供しているというような認識でございます。
◯竹内 愛
そこが何でそういうふうになったのかちょっと、学校の教育課程の時間も変動になっていますので、そういったことで、低学年のお子さんも長く学校のほうで授業があるという場合があるのかもわかりませんけど、少なくとも昨年度までは、きらきらのお子さんでも、さんさんのお子さんがいる中で、一定の配慮があって、事前に前倒しで補食の提供を行っていたということがあったということは、少なくともその段階では不公平感ですとか、アレルギーの誤食のおそれというのはないようにカバーできていたのではないかなと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
大変申しわけございませんでした。今年度も4校ほど補食を早めたというようなものが出てまいりました。申し上げますと、中台、上板、赤塚新町、志村小学校でございまして、1年生のみ、なれていただくために補食をこの4校だけ早めたということでございます。
◯竹内 愛
ちゃんと調べてからお答えいただいていいので、私としては、可能であればやっていただきたいなというふうに思っているんですよ。少なくとも、そういった工夫で、不公平感ですとか、アレルギーの誤食のおそれというのは回避できるだろうと。実際にやってきているので、そういうことを理由にできないというのは違うんじゃないかなと。むしろ、制度上の問題で、5時以降じゃないと、きらきらのお子さんの専用室ですね、きらきらのお子さんだけが使える部屋というのが5時以前はありませんので、そういった制度上の問題で5時というふうな時間になっているんではないかなというふうに思うんですよ。その点についてはいかがですか。
◯地域教育力推進課長
17時に補食を提供する理由につきましては、先ほど来ご説明しているように、公平感、不公平感、それから交流の時間、それからアレルギー対応、この3点で時間のほうは決めさせていただいているということでございます。
◯竹内 愛
わかりました。そうしたら、学童のとき、それから放課後の開放事業をやっていたときがありますよね。そのときは、校庭で、校庭開放で遊んでいるお子さんがいて、当然学童も校内にあったところもありますので、校庭を一部併用しながらお互いに使っていたと。そのときに、学童のお子さんがお部屋に戻っておやつを食べるということについて、相当な苦情があったということですか。公平、不公平だという苦情があったということですか。
それから、今、例えばちょっと前に前倒しをしている事業所さんではそういった声はないのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
大変申しわけございませんが、学童クラブの時代の苦情については、私のほうは承知しておりません。
それから、今の段階で、早く提供したときについて何かクレーム等が入っているかというお尋ねにつきましては、私どものほうに特に何か入っているということはございません。
◯竹内 愛
何をもって公平じゃないというふうに言っているのかなということなんですよ。だって、きらきらのお子さんは、契約をして、お金を払って補食を食べるわけですよ。そうしたら、当然補食を食べるお子さんと食べないお子さんとではそういう差がありますよということは説明がつくわけじゃないですか。ですよね。それで、公平じゃないって言われちゃったら、それはちょっと違うんじゃないかな。ほかのサービスだってみんなそうなんじゃないかというふうに思いますよ。だから、そこは行政の都合なんじゃないかなというふうに思うんですけど、逆に言ったら、そういう苦情が相当数あって、不公平だという観点からやめましたというんだったら、そういうふうに言ってもらったらいいんですけど、私は今までそういうふうな不公平だという声を多数いただいていますという声を聞いたことがないので、そういう認識では違うんじゃないですかということをお話ししているんですけども、いかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
さんさんのお子さんも補食についていただくようになれば、公平というような観点になろうかと思います。この辺は、竹内委員と私と大分感覚的に違いがあるのかもしれませんけども、給食費を払わない子どもは、じゃ、食べていいのか悪いのかの論争にまで発展しちゃいますので、私はそれ以上お話ししませんけども、やはり払わないから食べていい、食べていけない、公平か公平でないかといった場合は、私の感覚がずれているかもしれませんけれども、そういうような意見をお持ちになる方も一方でいらっしゃるのも事実でございます。そのようなことでご理解をいただければと思います。
◯竹内 愛
それは教育委員会としての見解として受け取っていいですか。というふうになりますよ。申しわけないですけど、今こういうことで、きらきらとさんさんではこういう事業の違いがありますよということを保護者の方にもご説明をして契約をしていただいているんですよ。さらに、補食は要りませんと言っている方は、きらきらのお時間にもいるんですよ。きらきらの時間にも補食は要りません、お金を払いませんといって、いいですよと認められて、その場にいるんですよ。食べていないお子さんも。そういうふうな線引きがされているんですから、そこは違うんじゃないですか。そこは制度としてきちんと認定をしていただいて、制度としてきちんと認められているから、そういうふうな制度が成り立つというふうに私は思いますので、そこについては、私はきちんとした教育委員会としての見解を持つべきだというふうに思います。
それで、最後に、ちょっとここは重複するので、それはちゃんとした教育委員会の見解について後でまた伺いますけど、つまり人手や場所が確保できれば、5時以前でも提供できるということではないかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
今、最後のお尋ねでございますけれども、人手、場所が確保できれば提供できるかどうかということでございますけれども、私のほうで再度検討させていただきたいと思います。
それから、先ほど来、教育委員会の見解かどうかということでございますけども、現時点では、お支払いしている方とお支払いしていない方がいらっしゃいますので、これは公平というふうに私のほうは申し上げるわけにはいきませんので、そこについては、補食のあり方についてもご理解をいただければと思います。大変申しわけございませんけども、私どもの考え方としてはそういうことになります。
◯竹内 愛
申しわけないけど、契約をしていて、お金を払っていないのに、食べている人の話をしていませんよ。そういうふうなことを言われちゃうと、ちょっと私は問題があるなというふうに思いますので、そこは訂正をしていただきたいと思います。
それから、利用者アンケートについてなんですけども、先ほど、お子さん方や保護者向けには満足度調査というのをやっていますということだったんですけど、公開については、窓口で公開しているというふうな言い方だったように思うんですけども、ホームページなどで公開しない理由についてお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
先ほどの説明がちょっと声が小さかったかもしれませんけれども、ホームページとあいキッズのフェイスブックと窓口とで公開をさせていただいているところでございます。
◯竹内 愛
それについては、ごめんなさい、私は詳細を見ていないんですけども、ここに書かれているように、個人情報を除いた範囲において公開をされているということで認識してよろしいでしょうか。
◯地域教育力推進課長
個人情報については一切出ておりません。
◯竹内 愛
その満足度調査の中身なんですけども、この陳情の要旨に書かれているような内容というのは含まれていますか。
◯地域教育力推進課長
設問ですけれども、あいキッズは楽しいですか、楽しいと思うものを教えてくださいとか、困ったことがあったときには先生に相談しやすいですかとか、あるいはプログラムの内容は適当でしょうかとか、そのようなことをお尋ねさせていただいております。ぜひ、そういうようなことであれば、私どものほうで集計したものがございますので、後ほどお届けさせていただきます。
◯竹内 愛
以前に見たかもしれないんですけど、よろしくお願いします。
今言われていた内容と少し違うかなと思うんですけれども、この中に書かれているようなことを設問の中に入れるということは可能ですか。
◯地域教育力推進課長
今年度また実施するときに、設問について検討のほうをさせていただいて、今までと余りにも違うと、またこれも対比もしづらくなりますので、その上で考えたいと思います。
◯竹内 愛
最後に、こちらの職員の方に利用アンケートを行ってくださいということなんですけど、私も職員の方に利用アンケートというのはどういうことなのかなとちょっと頭を悩ませたんですけど、ただ、ここに書かれていることを見ると、先ほど来質疑がありますように、職員さんにあいキッズの事業内容について提案をしていただいたらどうかという話が趣旨なのかなというふうに思うんですね。先ほど、偽装請負云々のお話もありましたけど、委託事業者が、区が協定書を結んでいる内容どおりに履行しているかどうかという立ち入りの検査は行いますよね。実際に職員の方にお話を伺うこともあると思うんですけども、その点はいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
お話を伺うことはあるかもしれませんけど、それに対して、こういうふうにしてください、ああいうふうにしてくださいというような指示等については、基本的にできないというふうに理解をして、お話のほうを伺っているというのが実態でございます。
◯竹内 愛
そうすると、お話は伺っているということですよね。となると、既に現場の職員さんに現場に行ってお話を伺っているのに、それをアンケートでやることがだめというのは理屈が通らないなと思うんですけど、なぜアンケートはだめで、直接現場に行って職員さんにお話を伺うのはいいのか、その点についてはいかがでしょうか。
◯地域教育力推進課長
現場に行って話を伺ってくることについてという前提条件の中で、きちんと履行がされているかどうか、区としてお願いしたことがやられているかどうかについての確認で、質問をするかどうかというお話でしたので、私のほうは、そういうお話は伺わざるを得ないので伺いますというふうにお答えしました。
ただ、ここで言っている設問については、若干違うのかなというニュアンス、私のほうは捉えておりますので、先ほど来申し上げているように、委託受託という関係の中で、いろんな質問をすることが適当かどうかというようなことで、私どもは不適当という考えで、この件に関してはやらないように、やるつもりはございませんというように答弁させていただいているところでございます。
◯竹内 愛
そうすると、じゃ職員の方に、実際直接お話を伺うということは、必要だというふうに認識されているということでよろしいですか。
◯地域教育力推進課長
よりよいあいキッズを進めるためには、ある意味当然のことでございます。これは、事業者あるいはその法人の責任者、こういう方通じて、常に今も受け取っているところでございますし、今後も継続して聞くべきことは聞いてまいります。
◯委員長
以上で、質疑並びに委員間討論を終了し、3件一括して意見を求めます。
意見のある方は、挙手願います。
◯安井一郎
まず、182号について、補食については、きらきらタイムとさんさんタイムに登録している子どもたちの交流時間の確保を図るために、提供時間は5時としているということは理解できるんです。
補食を食べると、食べる児童と食べない児童が、不公平感を持っては困るなというのもちょっと考え物なんですが、5時より前に考えていないようですが、今後の推移を見て、182号については、継続とさせていただきます。
183号については、28年度より実施している利用者満足度調査も継続して、円満な運営を行っているということなので、今後の推移を見て、これも継続とさせていただきます。
184号については、業務委託でもあるため、職員からのアンケートの実施は考えていないということなので、不採択を主張させていただきます。不採択。本当に、法人とのヒアリングをしながら、運営の質を高めていき、児童や保護者の満足度の向上を目指していただければと思いますので、184号は不採択とさせていただきます。
◯中野くにひこ
結論から申し上げます。
182、183を継続とさせていただきます。184は不採択でございます。
182の継続の理由でございますけれども、先ほど来の審議の中でも、5時に補食を出している区、出していない区、4時に出している区、出していない区、ございます。根拠性を、もう少しつまびらかにしていきたいなと。もう少しちょっと審議をして、判断をしていきたい。先ほどの公平感、公正感もございました。そういう意味でございます。
2点目は、利用者のアンケートでございますけれども、もう少し利用の、どういう要望があって、どういう形であいキッズ運営に反映されていったのか、もう少しちょっとつまびらかに審議していきたいなと、こう思っております。
3点目の不採択の理由でございますけども、先ほど来の理由で、協定書の内容から、私、お話を聞きました。竹内委員からのほうも、依頼者として、その業務を全うするために、本当に履行されているかどうか、従業員からヒアリングをする、それはもうやぶさかではない、当然のことながらやっていきます。ただ、アンケートについては、かなり強いものと言ったらちょっと語弊がありますけれども、聞くという形で、かなり偽装請負の、お互いのあるんではなかろうかと、こういうお話でございました。
故事の中で、李下に冠を正さずと、梨の畑の中では冠をいじくるんじゃないよと、盗んでいるように思われるということで、何を言わんとしているかというと、危うきことはやっぱりしてはだめだよと、勘違いされますよということなので、不採択とさせていただきます。
以上です。
◯高橋正憲
私は、182号については、今後の課題として、いろいろとまた話をし合いながら、いい方向に持っていければいいかなということで、継続を主張します。
183号、184号、私は継続を主張しますが、183号については、もう既に満足度調査とか、いろんな形で、利用者から話を聞いているということでありますから、既にね。陳情者に対して、僕は取り下げをお願いしてはいかがかなというふうに私は思います。
もう一つ、184号については、これ、偽装契約の、これはもう社会的に問題になった、そういうことでありますから、この提出者に対して、その旨をきちっと説明をして、取り下げてもらうということが、私は一番いいんじゃないかなと。知らない人は、このまま聞いちゃうと、そうだ、そうだというふうに思っちゃうんだけど、でも、契約事項の問題だったりすると、そうはいかないんですよ、やっぱり偽装契約ということでね。ですから、私はこのことをきちっと説明をして、議会事務局のほうで説明をして、本人にね、それで取り下げをしてもらうということが、私は一番いいと思いますので、とりあえずこの3つについては、継続を主張いたしますが、183号、184号につきましては、当事者に対して、きちっと取り下げをしていただけるように説明をしていただきたい、これを付与して、継続といたします。
◯高沢一基
陳情182号につきましては、他区の実態はまだ不明なところでありますし、全児童対策との関連性もまだ調査していきたいというふうに思っております。また、交流時間の確保や不公平感、アレルギー事故防止等についても、それを防ぐ手だてがないかどうかの研究、あるいは考察もまだまだ必要だと思いますので、継続審査を主張いたします。
陳情第183号及び184号につきましては、公開の方法等も、このような形でいいのかということと、あるいは、ほかに代替の手段がないかどうかもさらに調査したいと思いますので、継続審査を主張いたします。
◯松崎いたる
182号 あいキッズのおやつの時間を4時からでも可能とすることの陳情については、これ、まだ5時にやっているものを4時に改めてくださいと言ったら、まだ素直にわかるんですけど、結局ダブルでやってくださいという中身になってますから、それはちょっと、私は幾ら何でも無理なんじゃないかなというのが、今の、きょうのところの印象です。だから、不採択になりそうなんですけど、皆さんからの意見もまだまだ聞いてみたいので、継続といたします。
183号については、これは利用者アンケートは、満足度調査ということでやられているということですので、これも考え方2つあると思うんです。やってるんだから、議会もやれって言ってもいいじゃないかという考え方もあるかとは思うんですけど、ただ、議会がこの陳情を採択して、執行機関に送るとなると、ここに書いてあるような、アンケートの内容を聞けということになってしまうというのが、私はちょっとひっかかるところで、アンケートって、結構調査の方法、難しいと思って、結局この方、おやつの時間を何とか変えたいという意図が見えるわけですよ。実際問題、設問として、おやつの時間は何時からがいいですかということを聞くということになっているんですけど、でも、区はその時間帯を何時からがいいですかって聞くということだとしたら、時間を移せる準備があって初めて聞ける設問だと思うんですよ。区としては5時からやってますけど、4時に移しても、そういう声が多ければ準備ができてますよという準備があって、じゃ皆さん何時がいいですかって聞くんだったらまだわかるけど、5時と4時とか、4時からにしたらこういう課題があるとか、そういうことをやってる最中に、何時がいいですかって聞くのも、区がやるとしたら、ある意味無責任なところがあって、きちんとその要望に応えられるだけの余裕というか、準備があった上で、何時からがいいですかって聞くならわかるんですけど、今の段階、とてもそういう状況じゃないですから、それはまだこういう内容を聞くまでにはなってないなというふうに思います。
なので、この陳情については、今のところ、これやめたほうがいいんじゃないかなとも思ってんだけど、皆さんの意見も聞きたいので、継続とします。
最後、184号です。
これは、質疑の中で、私も問題点を言いました。これをこのまま、職員アンケートをやれば、その職員さんがどこの職場かというのも多分特定はできるだろうというふうにも思います。実際問題、それを隠して、区がそのアンケート調査をして、ネットに上げないまでも、じゃどうやって使ったらいいのかといったら、結局私の職場では、これこれこういうことがありました、こういうことを改善してほしいという声を職員から聞いたら、区はやっぱりそれをほっとくわけにもいかないから、おたくの事業者の中でこんなことあるという話をしなきゃ、そのアンケートをやっても使えないわけですよ。
だから、そういう意味では、職場の声を聞くという手段としても、アンケートをとるというのは、これは課題があるというか、いいことではないなというふうにも思いますので、そこまで言うと不採択なんですけど、皆さんの声もまだ聞いてみたいので、きょうは継続と。
◯竹内 愛
まず、182号については、採択を主張いたします。
私たちは、やっぱり利用者や利用児童の方々の生活の状況ですとか、利用時間、こういったことを加味をして、こういった事業というのは、つくられていく必要があるのではないかなというふうに思います。
先ほど来お話を伺ったところ、人手や場所が準備できればできるというふうに私は受けとめています。さらに、やっぱり5時がいいという方もいらっしゃると思うんですね。だけど、半分以上の方が5時前にお帰りになる、また、5時におやつを食べてすぐにお帰りになるという状況があることを考えると、やはり2段階でやるというのも一つの方法ではないかなというふうに思います。
この陳情理由に書かれているように、例えば、補食とおやつを別にして2回提供するということとか、こういったことについては、違うなと思うんですけど、陳情の要旨では、5時からだけでなく、4時からでも可能にするようにしてくださいってことなので、私としては、そういった可能性を追求できるようにやっていただきたいというふうに思います。
183号についても、採択を主張したいと思います。
先ほどの質疑の中で、今児童や保護者向けに満足度調査をやっていますということ、さらに、アンケートの内容についても、いろいろな意見を参考にして、これから策定をしていきたいということですので、この方の、例ってあくまでも例示ですので、要旨でいえば、利用者アンケートを行って、その結果についてホームページなどで公開をしてくださいということですので、この要旨に照らせば、今やっている満足度調査をさらに充実させた内容ということで、できるのではないかなというふうに思いますので、採択を主張したいというふうに思います。
最後なんですけど、184号についてなんですが、私は職員さんに直接意見を聞くというのは非常に大事だと思うんですね。現場に行くと、職員さん、やっぱり直接の、強いものがって先ほど課長おっしゃいましたけど、現場で働いている職員からすれば、強いものというのは、直接人事権があるのは事業所さんじゃないですか。事業所さんがいる前で、なかなか本音が言えないとか、そういったこともあると思うんですよ。そういったときに、直接区がいろいろな声をいろいろな形で聴取するという方法というのはあっていいんではないかな。
ただし、先ほど来危惧もありましたけど、区のホームページなどで公開するというと、先ほどどこどこのあいキッズの職員がというふうになってしまうと、やっぱりそれはいろいろ課題があるのかなと思うのと、アンケートの内容についても、この内容だけではないので、やっぱりいろいろな視点というのも必要になってきますし、いろいろな聴取の仕方があると思うので、この点については、この陳情のとおりというのは、なかなか難しいのかなというふうに思っていますが、いろいろな形で職員さんの声を聞いていただきたいということで、それを努力していただきたいということで、今回は継続としたいというふうに思います。
(「意見を言っているときに、何かいろいろ言われるとうるさい」と言
う人あり)
◯委員長
意見をいただきましたけど、先ほどの高橋委員の意見の中で、陳情者に取り下げ等の接触って言われたんですが、もう意見に入っちゃってますので、ちょっと時間的に結論を出さずして、陳情者に意見を聞くというのはでき得ませんので、今回はご理解をいただいて、先ほどの意見の発表のとおり、3本とも継続という意見で承知いたしますので、よろしくお願いします。
(「いえ、そのとおりでいいんです。決めたとおりですから」と言う人
あり)
◯委員長
以上で、意見を終了いたします。
本件については、意見が分かれておりますので、それぞれ表決を行います。
初めに、陳情第182号 あいキッズのおやつ(補食)提供時間を午後4時からでも可能とすることを求める陳情及び陳情第183号 あいキッズの利用児童等にあいキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第182号及び第183号を継続審査とすることに賛成の方は挙手を願います。
賛成多数(7-1)
◯委員長
賛成多数と認めます。よって、陳情第182号及び第183号は継続審査とすることに決定をいたしました。
次に、陳情第184号 あいキッズ職員にあいキッズ利用アンケートを行い、その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
陳情第184号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。
(「高橋委員も継続ってさっき言ってましたよね」と言う人あり)
◯委員長
継続。
(「183号でしょう」と言う人あり)
◯委員長
4号。
(「184号です。182と183は一括でやったので、今184」と言う人あり)
可否同数(4-4)
◯委員長
可否同数と認めます。したがいまして、委員会条例第14条第1項の規定により、委員長裁決をいたします。
陳情184号を、継続審査とすることは否決いたします。
この際、継続審査を主張される方で、特にご意見があればお伺いいたします。
◯高沢一基
継続審査が、委員長のご裁決で否決をされてしまいましたので、態度を表明したいと思います。
本陳情については、先ほどもちょっとありましたが、まず公開の点について、ホームページ上で公開が適切かどうかという大きな課題が、この陳情には存在することは事実だろうと思います。
あと、アンケート以外の代替の手段がないのか、こういった内容を見たときには、私はこの内容であれば、職場、法人のヒアリングだけに頼るというのは、私はちょっと違うのかなという気持ちがありまして、やっぱり現場訪問、職場に行くことによって、区として十分に意見を聴取することはできるのではないのかなと思いますので、代替の手段も確保されておりますので、本陳情については不採択を主張いたします。
◯松崎いたる
継続審査、否決をされましたので、採決をしなければならないんですが、皆さんの声を聞きたいと言ったんだけど、それがかないませんから、この場合、私の考えを述べさせていただきたいと思いますが、この陳情は、どなたか言ってましたけど、職員さんの声を聞いてくださいという、ざっくりとした趣旨ならば、これは反対するものじゃないので、それはむしろやっていただきたいんですが、陳情はあくまでも陳情で、ここでこれこのとおり、こういう項目について聞いてください、しかも、インターネットに上げてくださいというところまで書かれている陳情ですから、板橋区議会の場合、これ趣旨採択というのがなくて、陳情を採択したら、この文面をほとんど変えずに、このまま執行機関に上げなきゃいけない。それは幾ら何でも無理があるんじゃなかろうかというふうに思います。
願わくば、この陳情者に、私も一回この陳情を取り下げていただいて、出すとしたら、この委員会なりに、執行部宛ての意見書なり、一からやるとかいう方法ならわかるんですけど、この陳情を採択をして、それを執行機関に送るということでは、この内容はいろいろと欠点がありますので、そういった理由で不採択といたしたいと思います。
◯高橋正憲
私も、継続という話で、相手に対して取り下げてもらってはどうかという話をさせていただきました。
この184号につきましては、あいキッズ職員に対しての利用アンケートという話は、これはもしかしたら、職員の方々は自分たちの労働条件についてこうしてくれ、ああしてくれというような、そういう話になるとも限らないんですよね。
もう一つ、契約のことをいえば、その相手がこうしたい、ああしたいとなると、契約してきた問題と逆に今度偽装の関係になってしまうというような、そういうことがあったので、私はあくまでも、一旦は継続にして、そして、次の時点で、本人に対して話をして、それでもなおかつ理解しないで、出すというときに、僕は否決をしようかなというふうに、そういうふうに思っていたんです。
ですから、今回否決をされてしまったので、最後のそういう私の思いも消えてしまったので、そういう意味では否決ということにさせていただきたいと思います。
◯竹内 愛
先ほどの意見開陳の中でも、この陳情について危惧する部分として、公開の方法についてお話をさせていただきました。
やはり、前の183号との違いでいうと、アンケートの対象者が限られるということだと思うんですね。私は、職員さんに、実際に現場で悩まれていることですとか、どうしたら改善できるかということは、やっぱり意見を出していただくというのは非常に重要だと思いますし、意見を聞くということは、区としてやるべきだというふうに思います。
ただ、公開ということでいうと、それをそのままアンケートをやって、ホームページで公開するというのは、やっぱりいろいろな問題も出てくるだろうというふうに思いますし、職員の方々に聞く機会としては、アンケート以外の方法も検討することができるというふうにも思いますので、今この段階で判断をということであれば、これは不採択を主張したいというふうに思います。
以上です。
◯委員長
それでは、陳情第184号を採択する人はいないんだよね。不採択に。
採択することに賛成の方は挙手願いますたっていないんだよ。
(「それを言わないと次に」「言わないと、採択優先だから」と言う人
あり)
◯委員長
お諮りいたします。
陳情第184号を採択することに、賛成の方は挙手願います。
(賛成者なし)
◯委員長
賛成者なしと認めます。よって、陳情第184号は不採択とすべきものと決定いたしました。
ありがとうございます。
—————————–